「一度辞めた人は、私たちの会社でも長続きしないのではないか?」
その一言が、まだ見ぬ才能との尊い出会いを、そして企業の未来そのものを、どれほど閉ざしてしまっていることでしょう。それは、あまりにもったいない、そして少しだけ悲しい現実かもしれません。
この、採用市場に深く根を張る先入観という名の霧を晴らすため、20代の若者たちと長年向き合い続けてきた株式会社学情が、登録者数340万人を誇るビジネス映像メディア「PIVOT」という大きな舞台で、静かに、しかし力強く、一つの真実を語り始めました。
その「短期離職」は、“失敗”ではなく、自分を知るための“学習”だったのかもしれない
学情がPIVOTで丁寧に紐解く「第二新卒 隠れた真価と人材の発掘術」。その物語の根底に流れるのは、第二新卒という若者たち一人ひとりが歩んできた道のりへの、深い理解と共感に満ちた眼差しです。
従来の採用市場では、「短期離職」という経歴は、時にネガティブなレッテルとして扱われがちでした。しかし、学情は私たちに、全く新しい、そして温かい視点を提示してくれます。
- 彼らが手に入れた、真剣な“キャリア観”: 新卒で入社した会社とのミスマッチは、彼らにとって決して“失敗”ではありませんでした。それは、「自分は何を大切にしたいのか」「どんな環境でなら心から輝けるのか」を、実社会の経験を通じて真剣に考える、かけがえのない“学習”の機会だったのです。その経験は、彼らをより地に足のついた、誠実なプロフェッショナルへと成長させています。
- 社会人としての“基礎体力”と、真っ白な“吸収力”: 彼らは、基本的なビジネスマナーや仕事の進め方という“基礎体力”をすでに身につけています。それでいて、前職のやり方や文化に固執することなく、新しい価値観をスポンジのように素直に吸収する、真っ白な心も持ち合わせています。
- 胸に秘めた「次こそは」という、静かで強い情熱: 一度目のキャリアで悩み、考え抜いた経験があるからこそ、彼らの心の中には「次に出会う会社では、必ず貢献したい」「自分を信じてくれた人たちの期待に応えたい」という、静かで、しかし誰よりも強い情熱が燃えています。
つまり、第二新卒とは「問題がある人材」なのではなく、「自らの未来と真剣に向き合い、もう一度、勇気を持って一歩を踏み出そうとしている、可能性に満ちた挑戦者たち」と捉えることができるのです。
“宝物”と出会うために、私たちにできる、ささやかで大切なこと
では、企業はどうすればこの宝物のような人材と出会い、その秘めたる可能性を、共に花開かせることができるのでしょうか。動画の中で、学情の安野遼平マネージャーは、そのための心構えを、まるで語りかけるように丁寧に教えてくれます。
何よりも大切なのは、面接の場を、尋問の場にしないこと。彼らの過去の「点」としての退職理由を問いただすのではなく、彼らが未来に向かって描こうとしている「線」としてのキャリアビジョンに、心から耳を傾けることです。「その経験から、どんな大切なことを学びましたか?」「これから、どんな挑戦を通じて、世の中に貢献したいですか?」——。そんな温かい対話の中にこそ、履歴書には決して書かれていない、彼らの本当の輝きは隠されています。
そして、仲間として迎え入れた後も、彼らのポテンシャルを信じ、挑戦の機会を与え、成長を温かく見守る文化を育むこと。それこそが、彼らが安心して根を下ろし、やがて会社にとってかけがえのない大輪の花を咲かせるための、何よりの土壌となるのです。
企業の未来と、若者の未来を繋ぐ、温かい架け橋に
学情が、社会に大きな影響力を持つ「PIVOT」という場でこのメッセージを発信したことは、単なる自社サービスのPR活動ではありません。それは、日本のすべての企業と、未来を担うすべての若者たちの幸せな出会いを願う、彼らの誠実な想いの表れではないでしょうか。
人手不足が叫ばれる時代だからこそ、私たちは採用の「常識」という名の鎧を一度脱ぎ捨て、目の前の若者一人ひとりが持つ、無限の可能性に、もっと温かい眼差しを向けるべきなのかもしれません。その小さな視点の変化が、企業の未来を、そして社会の未来を、より優しく、より豊かに変えていくのだと、私たちは信じています。
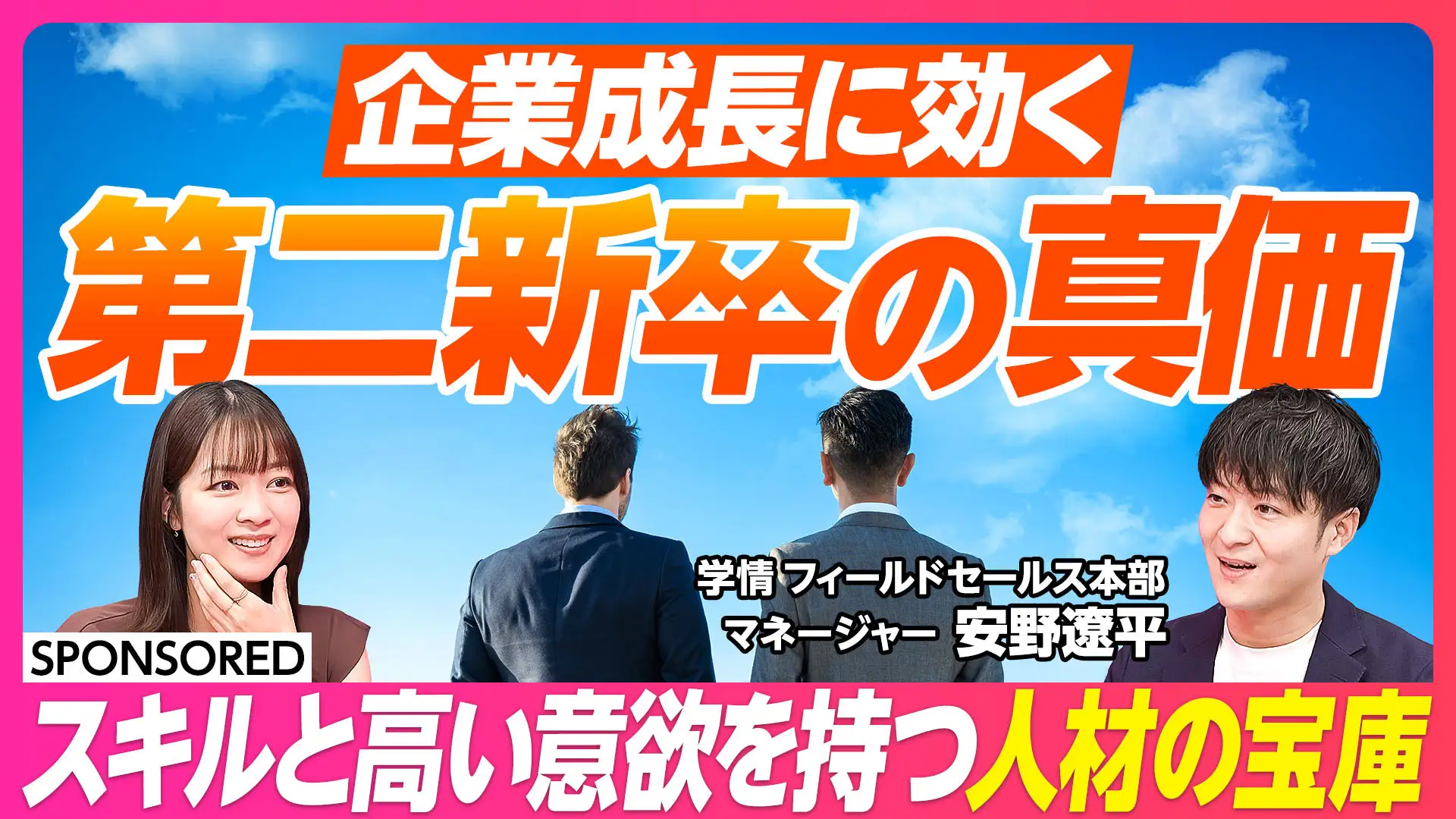


コメントを残す